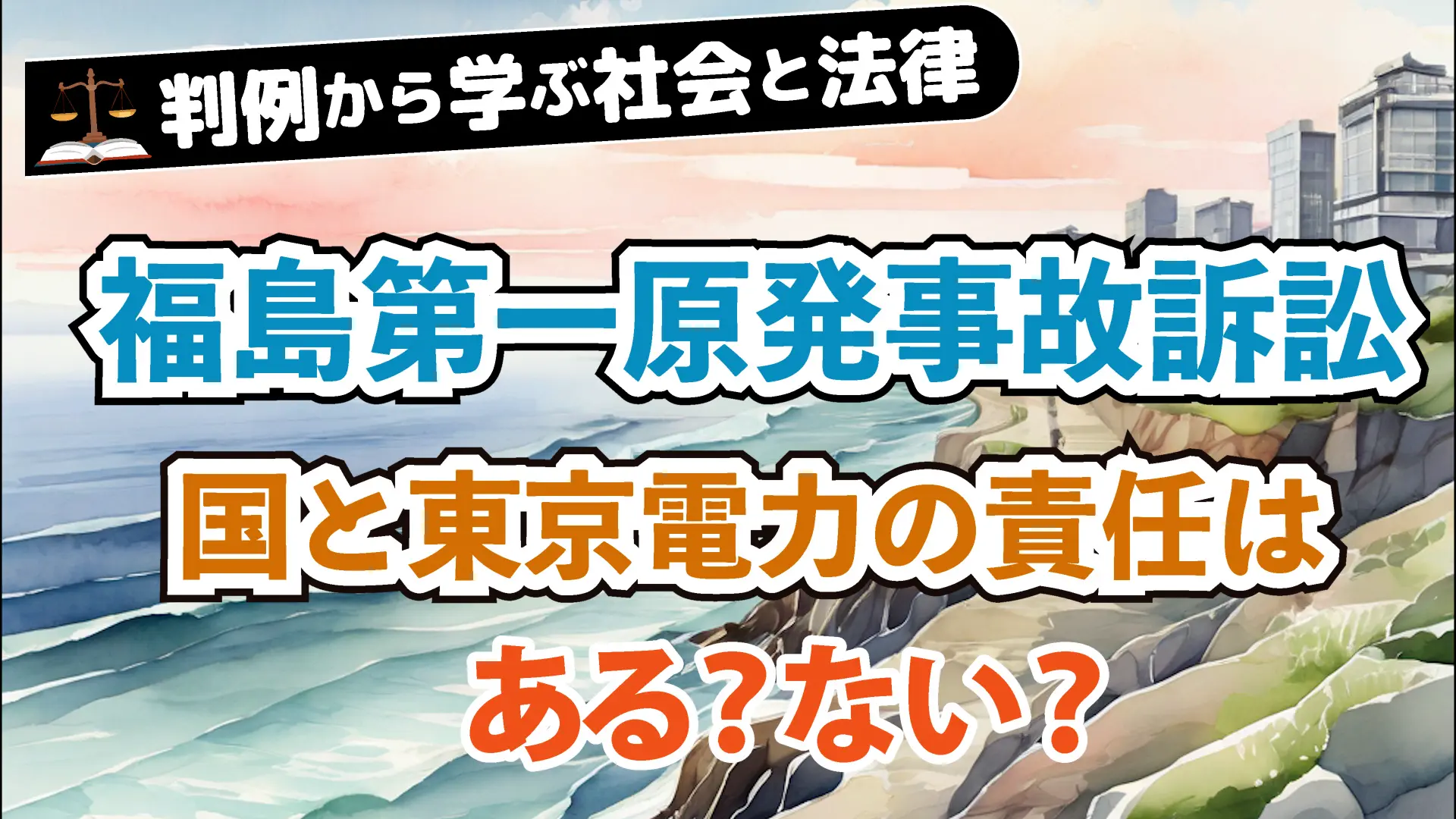
福島第一原子力発電所事故訴訟の詳細解説

令和1(ネ)801 損害賠償請求各控訴事件
令和5年11月22日 名古屋高等裁判所 名古屋地方裁判所
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/834/092834_hanrei.pdf
訴訟の概要
福島第一原子力発電所事故によって、避難を余儀なくされた住民や事故の影響で生活に支障をきたした人々が、国と東京電力を相手に損害賠償を求めた訴訟。
この訴訟は、国の規制権限不行使と東京電力の原子力損害賠償責任という二つの重要な争点を軸に展開されました。
原告と被告
原告: 避難住民や事故の影響を受けた住民。
被告: 国(経済産業省など)および東京電力。
原審では、一部の原告の請求が認められましたが、国に対する請求は棄却されました。その後、原告と東京電力がそれぞれ敗訴部分を不服として控訴しました。
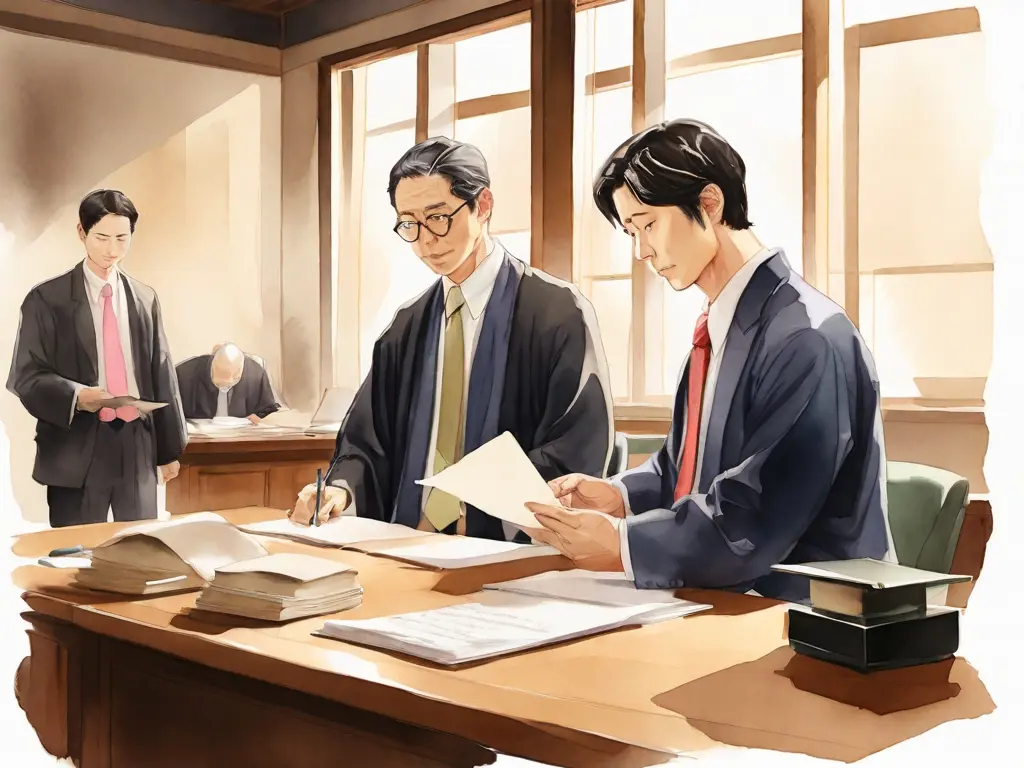
国の責任について
規制権限不行使の責任
裁判所は、国が電気事業法に基づく技術基準適合命令を適切に行使しなかったことが、事故の発生を防げなかった一因であると判断しました。
主な論点
1. 津波対策命令の欠如
2008年の津波試算に基づき、防潮堤や建屋の水密化措置を講じるべきであった。経済産業大臣は、技術基準適合命令を出すべきだったと指摘。
2. 予見可能性の有無
2002年末の長期評価によって、津波リスクの予見可能性が認められました。ただし、科学的知見の精度に限界があり、行政には一定の裁量が認められるとしました。
3. 事前警戒・予防の考え方
原子力規制では、危険がある場合には未確定な科学的知見を含めて対応する必要性が強調されました。
判決の結論
裁判所は、国が技術基準適合命令を発出しなかったことについて一定の違法性を認めました。ただし、科学的知見の限界を踏まえた裁量の余地も考慮されています。

東京電力の責任について
原子力損害賠償法に基づく責任
認められた損害項目
1. 避難費用
交通費、宿泊費、引越し費用。
2. 生活費増加費用
避難生活で増加した家賃や光熱費など。
3. 就労不能損害
事故で就労が困難になったことによる損害。
4. 慰謝料
避難生活や被ばく不安による精神的苦痛への補償。
損害賠償額の算定
裁判所は、原告個々の状況に基づき具体的な損害額を認定しました。ただし、東京電力が既に支払った賠償金は控除されます。また、損害賠償請求は世帯単位ではなく、個人単位で判断されました。

その他の争点
避難の合理性
裁判所は、原告の避難が合理的であったかどうかを慎重に検討しました。
- 乳幼児や妊婦など、放射線の影響を受けやすい人々については、避難期間を長めに認める傾向がありました。
- 一方で、避難の必要性がなくなった後の避難については、事故との因果関係が否定される場合もありました。
中間指針の問題点
原判決では、中間指針に基づく判断が避難者の個別事情を十分に考慮していないと批判されました。
- 被ばくによる健康不安を慰謝料の基礎から除外している点を問題視。
- 区域ごとの区分にも合理性の欠如が指摘されました。
判決の意義
2025年1月24日の判決では、国と東京電力の双方の責任が再確認されました。
この判決は、原子力事故における国家の規制責任や事業者の賠償責任の範囲を示す重要な事例として位置づけられます。
また、避難者の多様な状況に応じた柔軟な判断が求められることを浮き彫りにしました。
結論
この裁判を通じて、規制行政の透明性と即応性の重要性、そして被災者への適切な補償がいかに社会の信頼を維持する上で不可欠であるかが明らかになりました。今後の政策や訴訟においても、この判例が参考とされるでしょう。