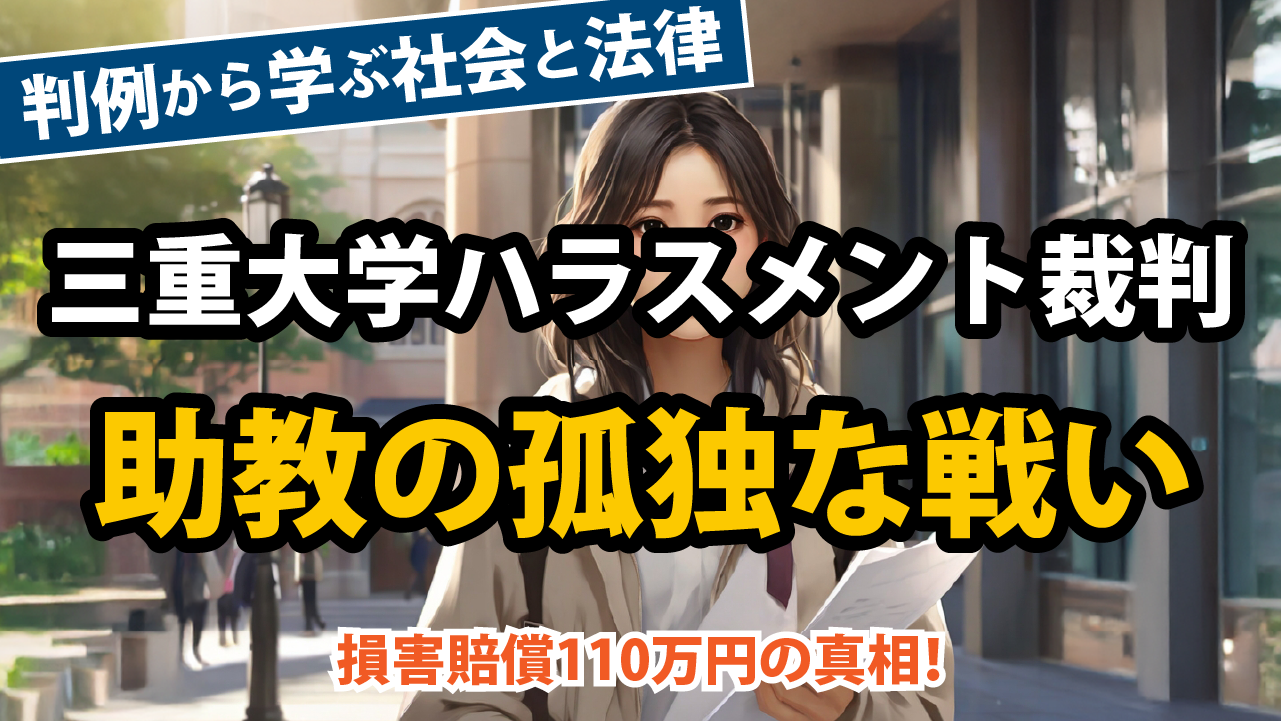
閉ざされた学舎の罠
令和5年(ネ)第839号 損害賠償請求控訴事件
令和6年10月3日 名古屋高等裁判所民事第2部判決
(原審 津地方裁判所令和2年(ワ)第564号)
裁判官 寺 本 明 広
裁判官 亀 村 恵 子
深い緑に囲まれた三重大学。その静寂なキャンパスの一角で、ひとりの女性研究者、A子助教は、深い闇に足を踏み入れていた。
それは、大学という閉鎖的な社会に渦巻く権力と、理不尽なまでのハラスメントの迷宮だった。
物語は、2008年4月1日、A子が三重大学大学院工学研究科の助教として採用された日に始まる。
建築構造学を専門とする彼女は、未来への希望を胸に、この学び舎に足を踏み入れた。
しかし、A子を待ち受けていたのは、輝かしい研究生活ではなく、大学という巨大な組織に仕掛けられた巧妙な罠だった。
A子が採用された「循環システム設計講座」の助教ポストには、本来、任期を設ける法的根拠は存在しなかった。
しかし、大学側は機械工学専攻との慣例的な取り決めを盾に、A子に5年間の任期を提示し、同意書への署名を迫った。
辞令交付の前日、突然呼び出されたA子は、建築学専攻長の執務室で、すでに用意された同意書に署名するよう指示された。
A子は抵抗を試みるも、大学側の巧みな話術と権力構造の前に、屈するしかなかった。
だが、A子の悪夢はこれだけでは終わらなかった。
A子が配属された執務室には、なんとウェブカメラが設置されており、彼女の執務状況が常時録画され、大学外の第三者もアクセス可能なシステムになっていたのだ。
地震発生時の状況を記録するためと説明されたものの、A子は着任時にその事実を知らされておらず、プライバシーの侵害に憤りを感じた。
A子の抗議により、カメラはその後撤去されたが、大学側に対する不信感は拭い去れなかった。
A子の孤立は深まっていく。指導教授はA子の意向を無視して変更され、建築構造学を専門とする彼女は、構造系から事実上排除される。
専門分野の異なる教授の下で、A子の研究は停滞を余儀なくされた。
さらに、A子は所属していた学内組織「さきもり塾」からも突然解任され、その活動実績をまとめた報告書にはA子の名前は記載されなかった。
まるで存在自体を抹消するかのような大学側の仕打ちに、A子は深い絶望感に苛まれた。
A子の身に降りかかる不可解な出来事の数々は、まるで緻密に計算されたシナリオのようだった。
誰が、何のために、A子を追い詰めていくのか。大学という閉鎖的な社会の闇の中で、A子は孤独な戦いを強いられた。
やがて、A子は自らの尊厳を守るため、そして、大学という巨大な組織の不正を暴くため、法廷で闘うことを決意する。
法廷という舞台で、A子は自らの体験を赤裸々に語り、大学側の隠蔽工作を暴いていく。
A子は大学という巨大な壁を乗り越え、真実の光を掴むことができるのか。
閉鎖された学舎で繰り広げられる、A子の孤独な闘いの結末は、私たちに何を問いかけるのか。

裁判所が認めた損害
裁判所は、原告であるA子助教が被った損害として、慰謝料100万円と弁護士費用10万円、合わせて110万円を認めました。
これは、以下の4つの違法行為によってA子助教が長年にわたり精神的苦痛を受けたことによるものです。
●任期に関する不当な取扱い及び不安定な地位の継続
●本件カメラによる盗撮
●構造系からの排除
●院生用研究室配分の拒絶
裁判所が認めなかった他の損害
しかし裁判所は、A子助教が主張した他の損害については、いずれも認めませんでした。
●平成22年から令和元年までの10年間分の、工学研究科における助教と准教授との給与の差額(請求額1200万円)
●工学研究科の教授らの不法行為により控訴人が対応を強いられた日当(請求額521万2500円)
●得られるべきであった研究費(請求額400万円)
●校費の計画的予算執行(年度内執行)が行えず執行できなかった費用(請求額91万9878円)
これらが認められなかった理由は、A子助教がこれらの損害を被ったことを証明する証拠が不十分であったためです。
裁判の根拠となった法律
裁判所は、原告A子助教の訴えを認め、被告である三重大学側に損害賠償を命じる根拠として、以下の法律を挙げました。
●国家賠償法第1条1項: これは、国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、故意または過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国または公共団体が、その損害を賠償する責に任ずると定めています。
本件では、国立大学法人である三重大学が「公共団体」に、その教職員が「公務員」に該当し、裁判所は、大学側の行為が国家賠償法第1条1項の適用上違法であると判断しました。
●民法第709条: これは、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。裁判所は、大学側の行為が、民法第709条に基づく不法行為に該当すると判断しました。
裁判所は、大学側の任期に関する不当な取扱い、ウェブカメラによる盗撮、構造系からの排除、院生用研究室配分の拒絶といった行為が、これらの法律に違反すると判断し、A子助教への損害賠償を命じました。
特に、任期に関する不当な取扱いについては、大学側が、A子助教に5年間の任期を提示した行為が違法であり、安全配慮義務違反にも該当すると判断しました。
これらの法律は、個人の権利や利益を保護するために重要な役割を果たしており、本件においても、裁判所はこれらの法律に基づいてA子助教の訴えを認めました。