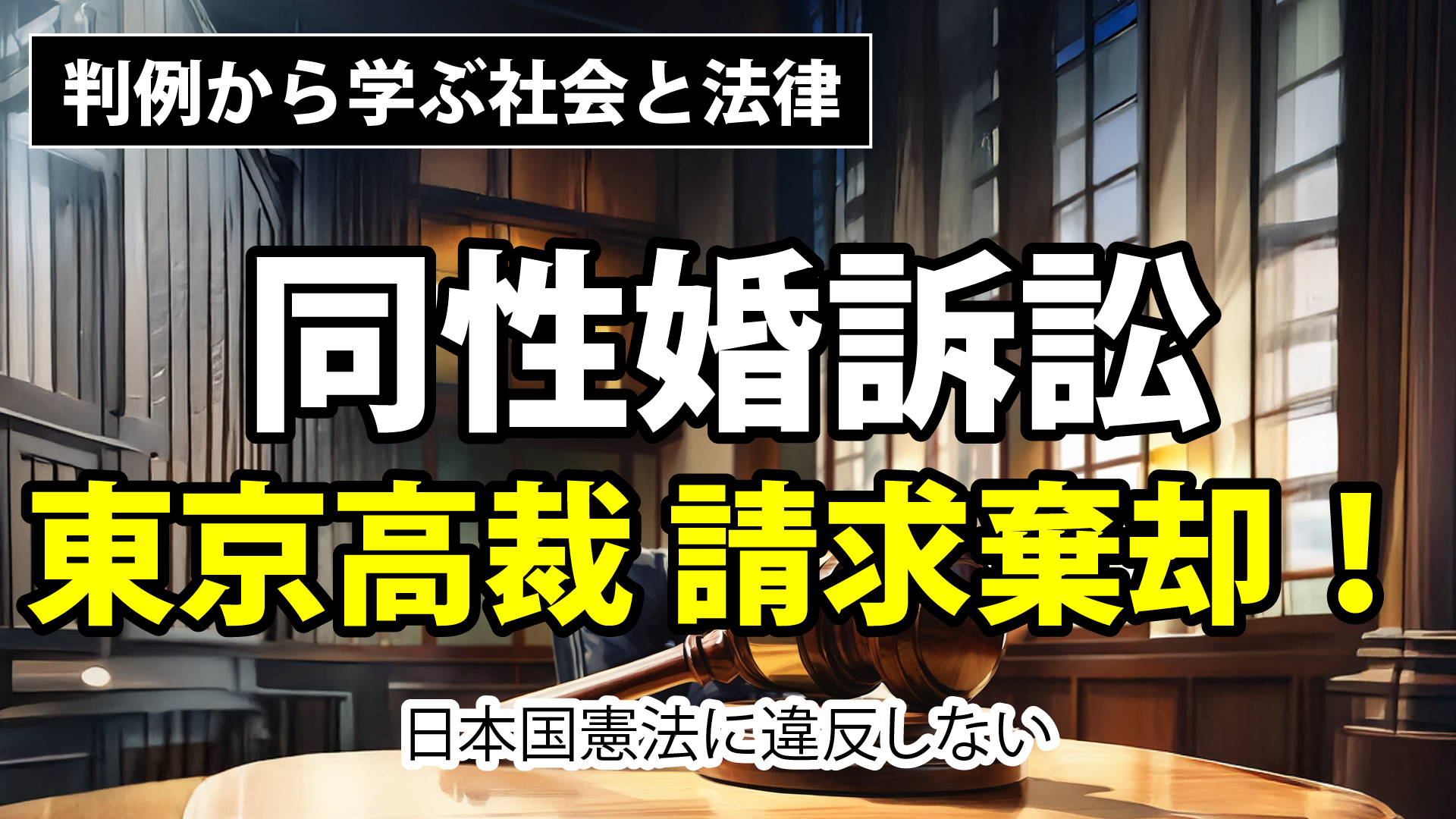
下級裁裁判例
令和5(ネ)292
令和6年10月30日 東京高等裁判所 棄却
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/093565_hanrei.pdf
2023年4月26日、東京高等裁判所は、同性婚を認めない現行の民法や戸籍法の規定は違憲だとして、国に賠償を求めた訴訟で、控訴人側の請求を棄却する判決を言い渡しました。
静まり返った法廷に、裁判長の言葉が重く響きます。今回の判決は、同性婚を求める人々にとって、大きな失望となったことは間違いありません。
しかし、裁判所はなぜ、このような判断を下したのでしょうか。本記事では、判決の詳細、そしてその背景にある法律、社会の動き、そして今後の展望について、分かりやすく解説していきます。
争点:同性婚と憲法
今回の裁判で争われたのは、同性婚を認めない現行法が、日本国憲法に違反するかどうかという点です。
控訴人である原告らは、同性同士で婚姻届を提出したにもかかわらず、不受理とされたことを不服として、国に損害賠償を求めました。 原告らは、憲法14条(法の下の平等)や 憲法24条(婚姻の自由)を根拠に、同性カップルにも婚姻の自由が保障されるべきだと主張しました。
一方、被告である国側は、憲法24条はあくまで男女間の婚姻を想定したものであり、同性婚を認めていないことには合理的な理由があると反論しました。
裁判所の判断:憲法違反は認められない
東京高裁は、憲法24条の「両性」という文言は男女を意味すると判断し、国側の主張を認めました。
裁判所は、憲法制定当時には、社会通念上、婚姻は男女間のものという考え方が一般的であり、同性婚は想定されていなかったと指摘しています。
憲法24条とは?
憲法24条は、婚姻の自由や家族生活を守るための重要な条文です。 この条文は、2つの項から構成されています。
1項: 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項: 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
つまり、1項では婚姻は男女の合意によって成立し、夫婦は平等な権利を持つべきだと定めています。
一方、2項では、婚姻や家族に関する法律は、個人の尊厳と男女の平等を基礎として作られなければならないと規定しています。
時代の変化と社会の動き
しかし、時代は変化しています。 世界では同性婚を認める国が増加し、日本でも性的少数者への理解が進みつつあります。
名古屋市が平成30年に実施した市民意識調査によると、自身が性的少数者であると回答した人は1.6%でした。 年齢層が低いほど、その割合は高くなる傾向がみられたことから、今後、性的少数者に対する理解はさらに深まっていく可能性があります。
裁判所の見解:国会の役割
裁判所は、同性婚を認めるかどうかは、最終的には立法府である国会の判断に委ねられるべきだとしました。
裁判所は、司法の役割を超えて、同性婚を認めるという判断を下すことはできないという立場をとったのです。
今後の展望:国会での議論
今回の東京高裁の判決は、同性婚を求める人々にとっては厳しい結果となりました。しかし、裁判所が同性婚の是非について判断を避けたということは、今後の国会での議論に期待を寄せたとも解釈できます。
同性婚を認めるかどうかの議論は、法の解釈だけでなく、その国ごとに、社会の価値観、家族のあり方、伝統文化など、様々な要素が複雑に絡み合っています。 国会では、これらの要素を踏まえ、慎重かつ丁寧な議論が求められます。