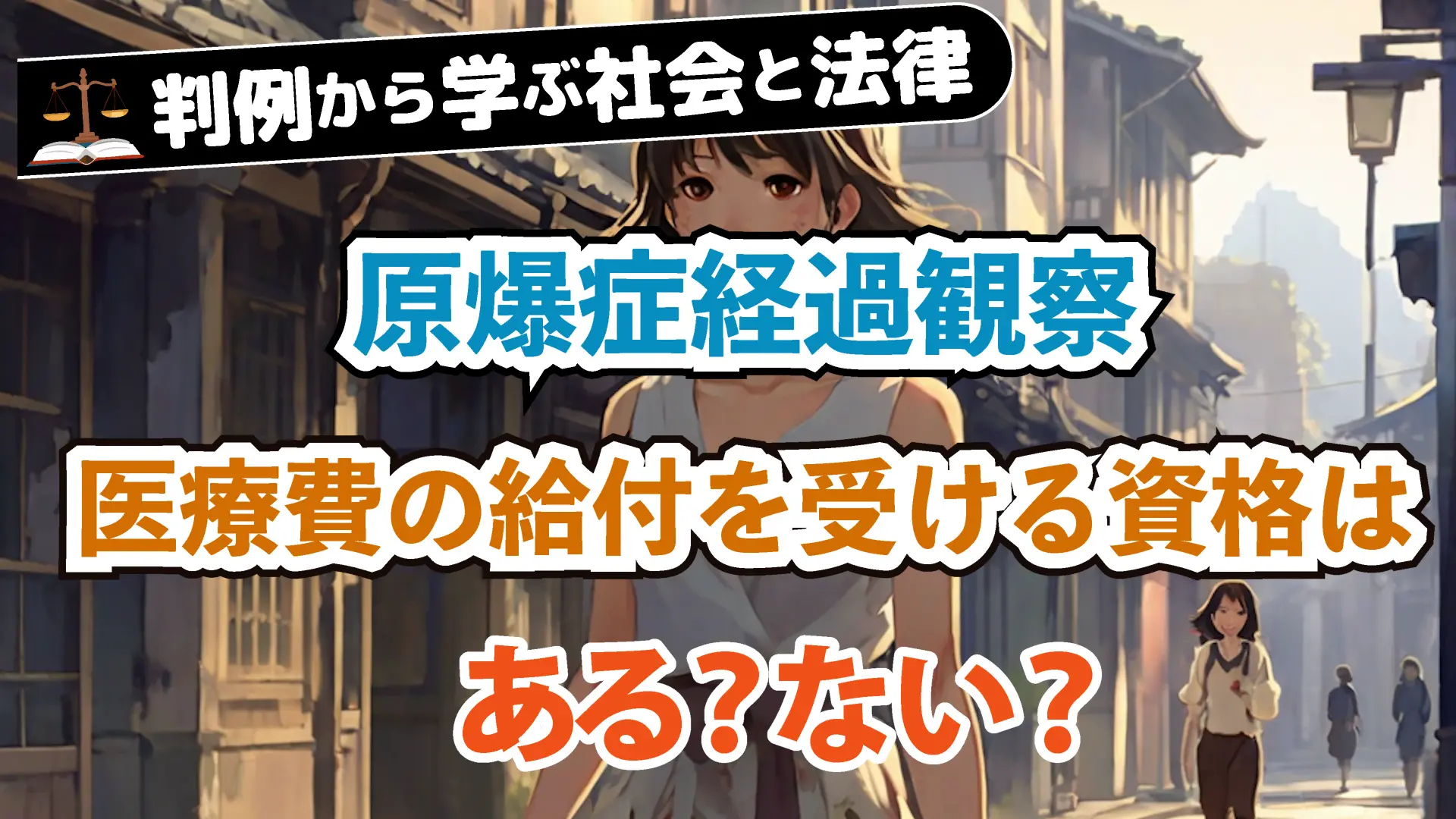
原爆症認定と要医療性に関する判決
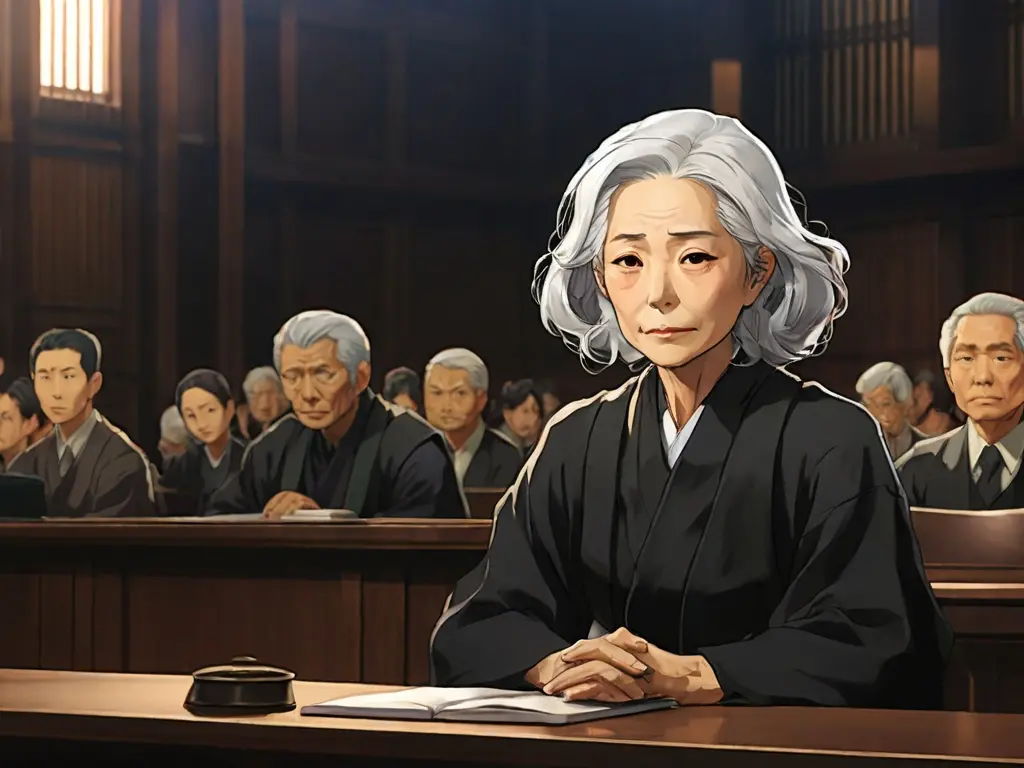
平成30年(行ヒ)第215号 原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
令和2年2月25日 第三小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/089255_hanrei.pdf
訴訟の概要
令和2年2月25日、最高裁判所第三小法廷で、一つの判決が下された。
それは、長崎の原爆被爆者である一人の女性が、国を相手に争った裁判の結末だった。
彼女は、被爆による病、慢性甲状腺炎が原爆症であると認定され、医療費の給付を受ける資格を求めていた。
しかし、裁判所が示した結論は、彼女の願いを退ける、厳しいものだった。
原爆症認定とは何か
この裁判の核心にあるのは、原爆症認定という制度だ。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下、「法」という)に基づき、被爆者が特定の病気で医療を必要とする場合、国がその医療費を負担する。
しかし、その認定には二つの条件がある。
一つは、被爆者が現に医療を要する状態にあること(要医療性)。
もう一つは、その病気が原爆の放射線によるものであるか、あるいは放射線以外の原爆の傷害作用によるもので、かつ被爆者の治癒能力が放射線の影響を受けていること(放射線起因性)だ。
今回の裁判で争われたのは、要医療性についてだった。
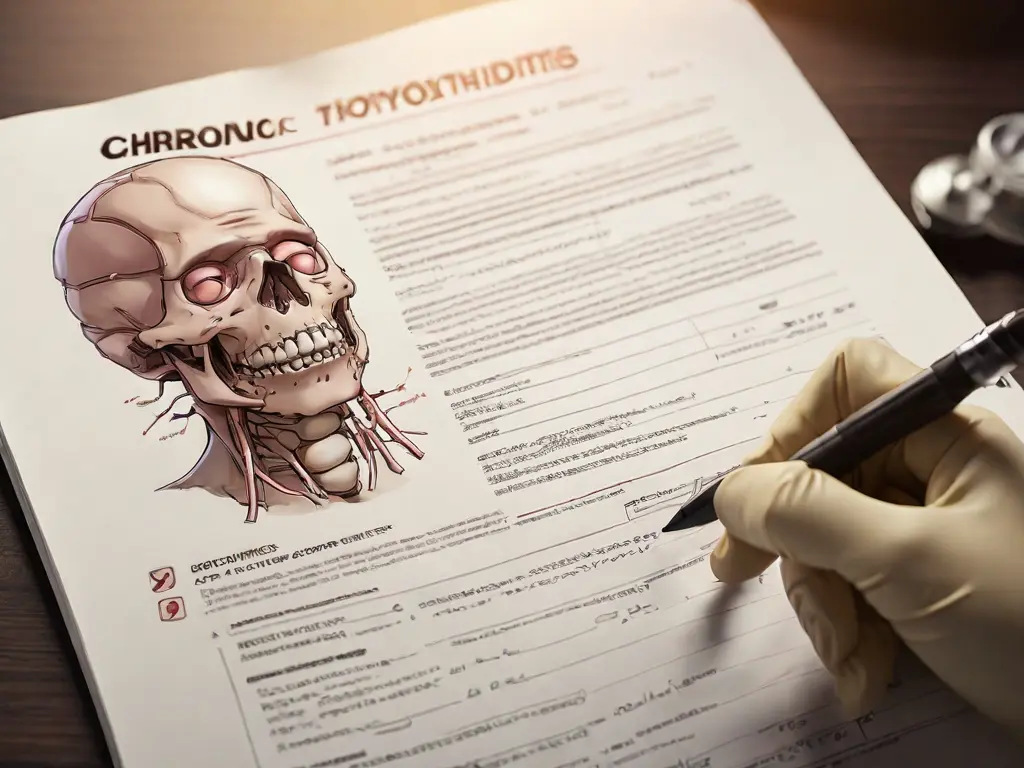
「経過観察」という名の壁
規制権限不行使の責任
この女性は、慢性甲状腺炎と診断され、長年にわたり「経過観察」を受けていた。定期的な診察や検査は行っていたものの、投薬などの積極的な治療は受けていなかった。原審では、この「経過観察」も医療行為であると判断され、要医療性が認められていた。
しかし、最高裁は、その判断を覆した。最高裁が示したのは、より厳格な基準だった。単なる経過観察だけでは、医療を必要とする状態とは言えない、と。最高裁の考えはこうだ。
• 法は、被爆者の状態に応じて段階的な救済措置を設けている。
•要医療性が認められない場合は健康管理手当、認められた場合は医療特別手当、後に要医療性が認められなくなった場合は特別手当が支給される。
•医療特別手当は、医療費だけでなく、入院や通院にかかる費用、栄養補給など、特別な出費を補うためのものだ。
つまり、医療特別手当は、現実に医療行為を必要とする人に、特に手厚い支援を行うための制度である。
その対象となるには、経過観察が、治療行為を目的とした、現実的な必要性に基づいて行われていることが必要だ。
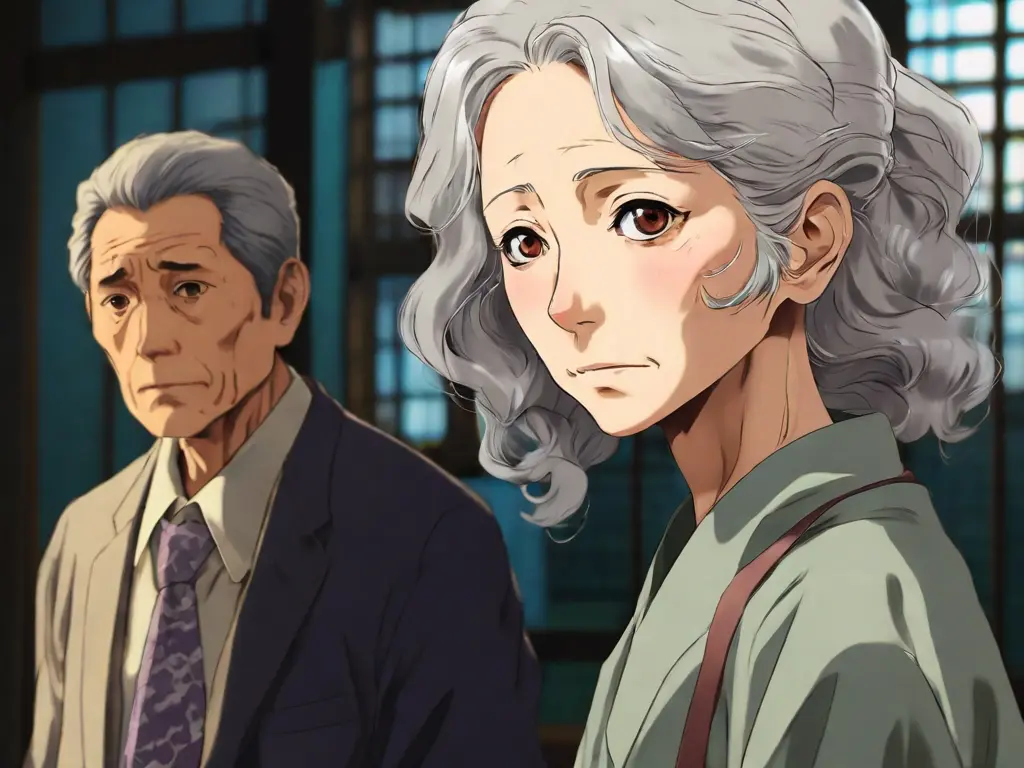
「特別の事情」とは何か
規制権限不行使の責任
最高裁は、「特別の事情」という概念を導入した。
それは、単なる経過観察ではなく、
• その病気が悪化・再発する可能性が高いこと
• 悪化・再発した場合、重大な結果を招く可能性があること
• そのために、経過観察が、治療行為に不可欠な一環として行われていること
これらの条件を満たす必要があると述べた。
今回のケースでは、女性の慢性甲状腺炎は、たしかに合併症や続発症のリスクがあるものの、甲状腺機能低下症に至る割合は低いとされた。
また、経過観察の内容は、問診や触診、必要に応じた検査にとどまり、積極的な治療は行われていない。
結果として、裁判所は、この女性の経過観察は、病状の悪化を確認するためのものであり、治療行為の一環とはいえないと判断した。
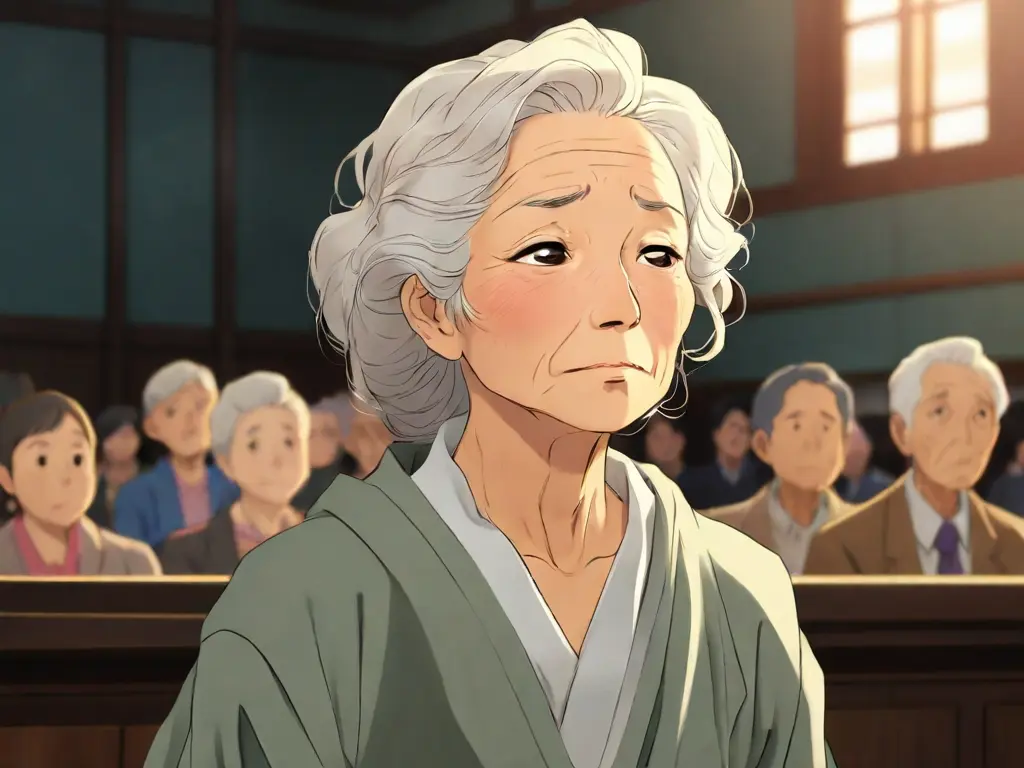
法律の解説
•1条: この法律は、被爆者の医療、健康管理、手当の支給等について定めている.
•10条: 原爆症の認定を受けた被爆者に対する医療給付について規定。
◦1項: 医療給付を行う対象者について「現に医療を要する状態にある」被爆者と定義.
◦2項: 医療給付の内容として、診察、薬剤の支給、医学的処置等を定めている.
•11条: 原爆症の認定申請について規定.
•18条: 医療費の自己負担額の支給について規定.
•19条: 医療機関の指定について規定.
•24条: 医療特別手当の支給について規定.
◦1項: 医療特別手当を支給する対象者について「要医療性が認められる」被爆者と定義.
◦4項: 要医療性が認められなくなった場合に特別手当が支給されることを規定.
•25条: 特別手当の支給について規定.
◦1項: 特別手当を支給する対象者について「要医療性が認められなくなった」被爆者と定義.
•27条: 健康管理手当の支給について規定.
•29条: 各手当の額の改定について規定.
最高裁は、これらの条文を解釈し、医療特別手当が、より積極的に医療を必要とする人に向けられたものであることを明らかにした。

「裁き」の後に残るもの
「被爆者に対する手当の仕組みの在り方については様々な議論があり得ると考えるが、現行法の解釈論としては法廷意見に賛成せざるを得ない。」
この言葉は、裁判官もまた、法の解釈と感情の間で揺れ動いていたことを示唆している。そして、こうも付け加えている。
「今後、疾病の状況の変化等の事情の変更により、上記の特別の事情があると認められる可能性を否定するものでも全くないことを強調しておきたい。」
つまり、今回の判決は、現在の状況における法の解釈であり、未来を閉ざすものではない、と。
この裁判が私たちに突きつける問いは、「救済」とは何か、ということだ。法は、すべての人を完全に救うことはできない。しかし、その枠組みの中で、最大限の努力をすることはできる。
この判決は、冷徹な論理で線引きを行うことで、かえって救済のあり方を深く考えさせる、そんな余韻を残す。
